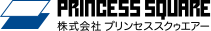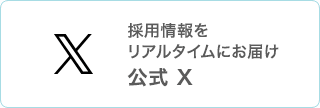吾唯足知 (われ ただ たるを しる)
2013年11月09日
京都の龍安寺の庭にある蹲踞(つくばい)に刻まれている「吾唯足るを知る」。数年前この蹲踞を見たときにはそう深く考えなかったのですがこの世の盛衰を見るにつけこの言葉の意味をかみしめることが多くなりました。
ヤマダ電機の中間決算が先日発表になりました。2013年3月期まで2年連続で減収減益の中、今中間期は遂に最終赤字との事です。上場以来M&Aを含め拡大路線を突き進み、2010年連結売上高2兆円を超えた家電量販店の雄が中間決算とはいえ赤字。企業としての一つのピークを過ぎたという事なんでしょうか。郊外型の家電量販店だったヤマダ電機が他の郊外型量販店を凌駕し、買収し、さらに都市の中心部にも出店、都市型量販店とも激突し勝っていく姿はまるで戦国時代の国盗り物語を見ているようでした。しかし売り上げ規模が大きくなるほど、必ずその売り上げに限界が来ます。
たとえが極端ですが、無限連鎖講(ネズミ講)がなぜ犯罪なのか。無制限に会員が増えることが前提であれば、ネズミ講は完璧なビジネスです。しかしそんなことは不可能です。1人の会員が5人の会員を勧誘し、その5人の会員がまたそれぞれ5人の会員を勧誘し・・・を繰り返していると12代目で日本人全員が勧誘されても足りません。それと同じように耐久消費財である家電製品を際限なく買い続ける人などいません。テレビを各部屋に付ける家庭はあっても、そのテレビを毎年買い替える家庭など皆無でしょう。日本国民の人口がピークアウトしている以上、需要が増え続けることは不可能です。私はそういう状況での規模の利益を求めるという事に漠然とした違和感を持ちながら家電業界を見ていたわけですがやはり来るべき時が来たという感じです。
ここからどう立直り、再び拡大路線を進むことができるかどうかが、社長の云う「第三の創業」となるのでしょうが、やはりそのテーマは量から質への転換ではないかと思うのです。
ナポレオン然り、ナチスドイツ然り、規模を永遠に追い求めていったものは必ず滅んでいっています。それは栄枯必衰の理なのでしょうか?ちょっと違う気がします。もしナポレオンが十分な準備をせずにロシアに攻め込んだりしなければヨーロッパは全く別の歴史になっていたでしょう。その失敗を知っているはずのナチスドイツも同じ過ちを繰り返し,それがきっかけで滅んでいます。
どんな組織でもどこかで足踏みをし、たとえそれが周りから見たら後退に見えても内なる体制固めを怠らないことが必要なんでしょうね。
易経で言うところの「亢龍(こうりゅう)悔いあり」です。
しかし、民主党政権時に打ち出した家電エコポイント制度、環境に大した影響がないだけでなくこの政策に振り回された家電メーカーにとっても罪な制度でしたね。あれがなければ家電メーカーの舵取りはもっと違ったものになったのかもしれません。