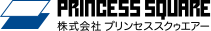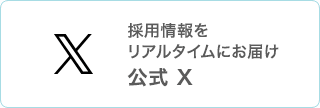情けは人の為ならず
2015年06月05日
この言葉は私の祖母が生前、口癖のように言っていた言葉です。「情けは人の為ならず、回りまわってわが身の徳」と言う、だから人には情けをかけてあげなさいと。
私にとってはこの言葉、それこそ耳にタコができるほど聞いていたので言葉の意味を違う意味ととらえている人がいるなど考えられませんでしたが、最近のテレビなどで違う意味で解釈している人がいるというのを聞き驚きました。この言葉、前半で終わってしまうと「情けは人の為ならず」情けは人のためにならないからかけるなという意味にも取れます。最初はその誤った考え方を聞いて、「もっと日本人は勉強しないと駄目だ!」等を思った時期もありました。が、その考えは時が経つにつけ少しずつ変化してきました。この社会で生きていく時間が長くなると、誤った解釈の仕方もまた真ではないかと思うようになったのです。
最近はあまり取り上げられなくなりましたが「義理と人情を秤にかけりゃ、義理が重たい浮世の定め」という言葉がはやった時期がありました。私見ですが人情とは人であれば当然持ち合わせている感情、情けです。どちらかと言うとこの感情は、一義的には親子、夫婦、家族、二義的には友人に向けられる感情です。義理とは、社会で生きていくために必要なルール、約束です。これは自然発生的に人間に備わっているものではなく、人が社会で生きていく過程でこのルールを教わり学んでいくものです。そして、義理は社会で生きていくには最も大切なものであり守らなければならないものです。仮に、人がもし人情を義理に優先させるようになると社会は混乱してしまいます。人であれば誰もが、自分の子供や家族が大切です。しかし、誰もが家族を優先させる生活をしたら、その家族の生活が懸かっている会社やコミュニティは一体だれが守るのですか?だからこそ、社会の構成員である以上、守らなければならない暗黙の約束があるのです。この義理の量は社会的立場が上がってくれば当然多くなります。社会経験を積めば積むほど、この義理が非常に大切だということを思い知らされるのです。
「情けは人の為ならず」でいうところの「情け」は人情の中でも一義的な親子、家族を指すのではなくもう少し広い意味での友人や知人、或はもっと広いコミュニティを指すのかもしれません。しかし、「情け」はやはり人情に繋がる部分が多く、人として当然持っている感情ですから、困っている人がいるとつい同情し「手を差し出すのが人の道」と思ってしまうのですが、それを実行したからと言ってその人が幸せになったかと言うとそれは自己満足で終わるケースのほうが多い気がします。助ける方法が悪かったせいもあるでしょう。結局、情けをかけることは本当の意味で助けることにならないのではないかと思うのです。
私が独立を考え、父に相談した時、父が言った言葉「お前に出してやれる金はない。しかし、事業に失敗したとき、住む部屋だけは用意してやる」、それが本来の「情けは人の為ならず」なんでしょうね。