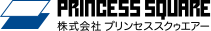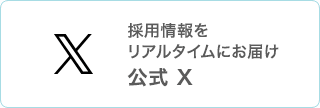最近の読書で
2009年06月22日
私の趣味のひとつが読書です。しかしこの読書、心の余裕に多分に影響されます。元来、歴史小説や推理小説が大好きで大学時代などは、「山篭り」と称して下宿先で大学にも行かず長編小説をむさぼるように読みました(おかげさまで留年してしまいましたが)。しかし、社会人になり読める時間が限られてきて、しかも読まなければならない本、読みたい本が次々と出てくる中で中々歴史小説や推理小説を読む時間を確保することができず、読むとしたら一年に3回ある長期休暇の時となってしまいました。頭の中に「仕事」が入ってくると落ち着いて読めないのです。読んでいてもいつの間にか仕事のことを考えてしまって同じところを何度も読み返しているうちに嫌に成っちゃうんですね(なんとも器の小さい男です)。しかしながら最近面白く読めた歴史読本がありました。半藤一利さんの「幕末史」です。幕末、ペリーの来航から始まって、西南の役までの24年間をドキュメントタッチに書かれていて中弛みすることなくあっという間に読み終えました。特に面白かったのが、黒船の来航かという外圧を受けてから日本中がそれこそ蜂の巣をつついたようになり、やれ尊皇攘夷だ、公武合体だ、果ては尊王倒幕だ、と大騒ぎするのですが、色々な勤皇の志士といわれる人たちの中で早い時期から藩という範疇を越えて「日本」という大きな括りの中で発言し行動していたのは勝海舟ただ一人だったのではないかというところです。人間、やはり所属している部門を背負っているわけでその範疇を取り除いて大局を見て行動をとることは非常に難しいのでしょうね。まあ勝海舟は幕臣ですから薩摩藩や長州藩のように地方の藩出身の人と比べ藩としてのナショナリズムの影響を受けなかったのかもしれません。現代で言えば、東京出身の人は地方の人より地方というフィルターがない分、日本を語れるみたいなものですかね。しかし、24年ですよ。24年で鎖国をしていた江戸時代から明治維新を通り越して西南の役まで行っちゃうんですからね。時代は激変するものです。今の常識が20年後には非常識になっていることがたくさんあるんでしょうね。ただ変わるようで変わらないものもたくさんあるものです。もう少し、短い括りでの話をします。最近の出来事です。今から10年前の平成11年の頃、私どもの会社が所有していた物件を処分しました。白金のマンションです。築年数はその当時で30年経っていました。その物件が何の因果かまた私たちグループで購入することになりました。リフォームをして販売した値段は・・・・(回答は営業マンにお聞きください。)この間、色々な評論家や雑誌、新聞で不動産は上がる、下がる、人によっては暴落するなどと書かれ、騒がれました。その上平成13年、平成20年のマンション不況を乗り越えて結果は成約事例が語っています。大局的な立場で見るということは大切ですね。