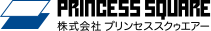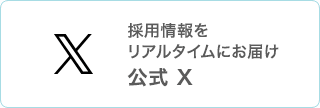ブラック部活
2016年02月25日
何でもかんでもブラックとつけるのですね。今日、朝テレビ番組で「ブラック部活」の放送をしていました。今回のブラックは顧問の先生が訴えているものです。公立中学の部活の顧問の先生が部活動のせいで休みが取れない、休日練習があってそれに立ち会っても残業代が出ない、そのせいで自分の家庭に影響を及ぼすことを考えると将来に不安が残るというものでした。
事の善悪を語るつもりはありません。しかし、時代は変わりましたね。
「ALWAYS 三丁目の夕日」という映画がありました。時代は昭和33年、日本が高度経済成長に差し掛かったころです。私は、昭和37年生まれですからその時代は私の父が30歳前後、父が勤めていた会社が創立したのが昭和24年ですから会社にとっても一番頑張らなくてはならない時期だったでしょう。私は子供の頃、父の武勇伝をよく聞かされました。その時代の父たちの世代の日本の会社はすべて、それこそ今で言うところの「ブラック企業」だったでしょう。父の会社は卒業アルバムの会社だったので、学校の卒業式が近づく1月、2月は24時間印刷機、製本の機械を動かさなければなりません。今でこそ2交代制、3交代制は当たり前なのでしょうがその当時はそれぞれの機械を一人だけで担当していたといいます。父は「俺は24時間の徹夜を何日も続けてやったけど機械に指を挟まれて指を落とすことがなかった!」と自慢していました。また、私の兄が生まれた時(兄は残念ながら生後6か月で夭折しました。)父は北海道に売掛金の回収に行っていたようです。とにかく回収できるまで帰らないと決めて北海道に滞在しているときに子供が生まれたので子供の顔を見たのは生後10日経っていたそうです。煙草を買う金がなく落ちている吸い殻を拾ってきて、葉っぱを巻きなおして新たな煙草を作ったり、風呂に入る金がないからとドラム缶拾ってきてそれにお湯を入れて五右衛門風呂状態で入浴したりと、今じゃ考えられないことばかりです。残業時間といえば1か月恐らく300時間を超えていたでしょう。しかしそれが父の誇りであったのです。私が成人になり父とカラオケスナックに行ったとき、父の十八番は村田英雄の「王将」です。「吹けば飛ぶような将棋の駒に欠けた命を笑わば笑え!」の「将棋の駒」のところを自分が勤めている会社名に変えてコブシをつけて歌っていました。その歌を歌っている父は輝いていました。私にはそれが何ともかっこよく、いずれ私自身もそうやって会社に命を懸けられる人間になりたいと密かに思っておりました。
そうやって、父にあこがれて社会人となり「自分が命を懸けたと言えるに足る会社を作る」という思いで今も会社を運営しています。
「ブラック〜」と言う時、労働をどうとらえるのかによっても変わってくるのでしょう。「労働を労働時間の切り売り」と考えるのか「労働は人生の達成感を得るため」によっても大きく変わってくるのでしょう。やらされていると考えて仕事をするとやはり心の病につながっていくのでしょう。父の時代は生きていくのに必死の時代だったのでしょう。長時間労働云々と考える余裕がなかったのかもしれません。
時代は変わりました。