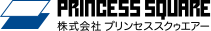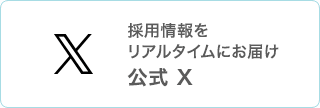京都にて
2012年03月08日
私は、生まれも育ちも大阪で大学で東京に出るまで18年間、京都に近いところに住んでいながら一度もプライベートで京都観光と云うものをしたことがありませんでした。もちろん遠足や社会見学で中学校時代、金閣寺、銀閣寺に行った事はありましたが決して能動的なものではなく、ましてや30年以上前の話ですからほとんど記憶にありません。今回、機会に恵まれ初めて京都観光をしてきました。(元関西人としてはあまりにも遅い時期ですが・・・)
シーズンオフということもあり比較的すいていました。仏像では三十三間堂、大原の寂光院で大変感銘を受けましたし、庭園では金閣寺、銀閣寺、三千院、宝泉院、天竜寺には圧倒されました。平安時代から続く歴史の重みを痛感させられました。また、京都は大都市でありながら大東亜戦争中空襲が少なく、戦前の町並みが未だ残っている場所が多く残っておりそれが又古都のイメージアップに繋がっていました。しかし、京都の古い民家は確かに間口が狭くいわゆるうなぎの寝床の家が多いですね。何でも、玄関の広さで払う税金が決まったせいだとかと聞きましたが本当なのでしょうか。真偽のほどは分かりませんが、間口が狭いせいか家が密集して並んでいる感じでにぎやかに見えます。
又、気になったのが拝観料の高さです。一つの寺に行くと最低500円、中には1000円取る所もあります。維持管理にお金がかかるのは分かりますがあまりに高い気がしました。また車で移動するとどんな辺鄙な場所でも駐車料金が800円から1000円取られてしまいます。宿泊代等を考えるとえらい出費になってしまいますね。古都巡りしたいならお金を払えと言う事なんでしょうか。古都税の問題でも論議になった事ですがもう少し考えてもらいたいです。
そして、一番印象に残ったのがやはり法然上人が行った大原問答で有名な勝林院に行ったときです。京都にある寺院はどれも素晴らしいのですが、天台宗や禅宗の臨済宗はいったい誰のための宗教かと考えると、やはり貴族、武家階級の為と考えてしまいます。五木寛之さんの「親鸞」を読み、当時の庶民の生活を想像するとこのような素晴らしい寺院を作るお金があるのならもっと一般庶民を潤わせる方法があったではないかと。
一般庶民の救いを掲げた法然上人が命を賭けて問答に挑んだ寺を見ると我が身の小ささを思い知らされます。信念に生きた男がいてそれに共感した男がその志を引き継いでいく、なんとも美しい話です。
そんなこんなを考えながら京都巡りをしてきました。しかし、中学生の修学旅行でタクシーを使ってグループ行動している学校がありました。今では当たり前の光景らしいのですが、なんとも時代は変わったものです。子供がタクシーとは。